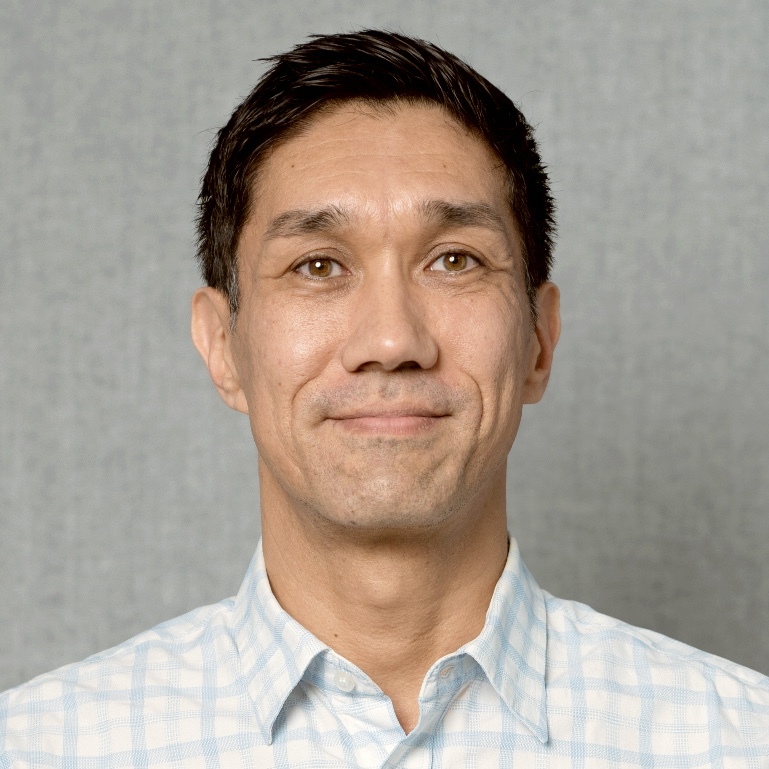行政や民間組織が提供するオープンデータは、誰でも自由に活用できるものだ。それが中小企業にとってどのように役立つのか、どのような注意点があるのかを庄司昌彦氏 (武蔵大学教授) に聞いて、オープンデータの有用性を検討した。

目次
オープンデータとは、自治体や公的機関、各種団体が保有する情報を公開し、自由に利用できるようにしたものを指します。誰もが手に入れることができる、一種の ビッグデータと言っても良いでしょう。
日本でオープンデータが大きく注目され始めたきっかけは東日本大震災だと言われています。「sinsai.info」のように、 復興支援のために被災地情報を収集・公開するプラットフォームが市民によって立ち上げられ、それが大きな反響を呼びました。現在は、行政の効率化や透明性向上の観点から、国・地方自治体のオープンデータ化が積極的に行われています。また、後述のように、ビジネスの場でもオープンデータの活用が進んでいますが、中小企業の間で十分認知されていないように見受けられます。
「オープンデータ伝道師」であり、長年に渡って中央省庁及び地方公共団体のオープンデータの取り組み推進に貢献してきた武蔵大学情報学部の 庄司昌彦教授への取材のもと、中小企業にとってのオープンデータの利点や注意点をまとめました。
オープンデータの定義
「 オープンデータ基本指針」では、オープンデータを「誰もがインターネット等を通じて容易に利用 (加工、編集、再配布等) できる」データと定義しています。また、以下のいずれかの形態に該当するものと定めています。
- 営利目的、非営利目的を問わず二次利用が可能
- コンピュータプログラムが自動的にデータを加工、編集等できる
- 原則的に無償で利用できる
公共データは国民共有の財産と位置付けており、「支障のあるデータ項目を除いて」オープンデータとして公開することを原則としています。
2012年に「電子行政オープンデータ戦略」が発表されたことを皮切りに、横断的検索を可能とする 各府省のデータカタログサイト「DATA.GO.JP」の運用開始 (2014年) や、国や自治体によるオープンデータの取り組みを推進する「官民データ活用推進基本法」の施行 (2016年) など、 オープンデータ環境の整備が着々と進められてきました。
さらに、新型コロナウイルス感染症対策の一環として、 スマホユーザーの位置情報に基づいた人流データや 空き病床数の可視化のような取り組みでオープンデータが有意義に活用されました。このように、オープンデータは社会課題の解決に大きな役割を果たしてきたわけですが、官⺠協働の推進を通じて、ビジネス界の諸課題の解決や、経済全体の活性化も期待されています。
それでは、事業者にとってどのような活用の仕方があるのかを見ていきましょう。
中小企業にとってのメリット①:低コスト
中小企業にとってのオープンデータの利点について、庄司氏は「行政機関が収集したデータや資料など、大きな組織力や正統性がなければ入手・作成できなかったデータを、低コストで入手できるようになるというのが大きなメリットである」と述べています。
定義上、オープンデータは無償で利用できるものだと先程述べましたが、実は維持費として利用料を徴収する場合もあります。それにしても、小規模事業者が独自で収集できるデータの量や範囲は、行政機関のそれとは比較になりません。
こう言ったオープンデータの (ほぼ) 無償提供の背景には、より良い公共サービスを目指す行政の意向がありますが、それと同時に、経済活性化の意図もあります。例えば、内閣官房と経済産業省が提供する 「地域経済分析システム」( RESAS) では、産業構造、人口動態、人の流れなどのデータがマップやグラフで表示されています。このようなデータを利用した民間企業は、製品・サービスの企画開発から広報活動に至るまで、さまざまな業務に活かすことができるでしょう。
活用事例 1
「標準的なバス情報フォーマット」に基づいたオープンデータ
沖縄県の「観光2次交通機能強化補助事業」は、公共交通機関の利用者増を図ることを目的としたプロジェクトです。国土交通省が2017年に公開した「標準的なバス情報フォーマット (GTFS-JP)」を用いて、県内51事業者から経路や運賃情報などを収集し、Googleで検索可能になっています。
中小企業にとってのメリット②:コミュニティの支援
当初より、オープンデータは シビックテック (市民参加型テクノロジー) の活動と深く関わっており、オープンデータを活用する人や団体・組織の間で、数々のコミュニティが形成されています。そこでは、データを使いやすく加工するためのツールがシェアされたり、活発な情報交換が行われたりします。このようなコミュニティの存在が、オープンデータのもう一つの強みです。
庄司氏は次のように解説します。「シビックテックコミュニティのFacebook・Twitter上での人的ネットワークやイベント、Slackでのやりとりも含まれますし、WikipediaやOpenStreetMapなどの投稿者・編集者のコミュニティ、さまざまなオープンソースソフトウェアの開発者や利用者の勉強会コミュニティ、交通オープンデータの団体や、データサイエンス等の学会なども含まれます。オープンデータにはさまざまな分野のものが含まれますので、それらの利用者がオンライン・オフラインさまざまなところにいて、ゆるやかにつながっています」。
例として、「アイデアソン」や「ハッカソン」と呼ばれる一連のイベントがあります。そこから、地域の課題を解決するアイデアやアプリケーションが生まれ、事業化に至る新規事業の創出につながる場合もあります。
活用事例 2
「LIVE JAPAN」の多言語災害情報
「LIVE JAPAN PERFECT GUIDE TOKYO」は訪⽇外国⼈向け観光情報サイトですが、付加サービスとして 災害時支援情報の多言語発信プロジェクトに取り組んでいます。東京都が提供するオープンデータを利用して、避難所をマップに表示させたり、施設からの災害情報を多言語で配信する仕組みです。
データの「原則共有」への転換
オープンデータの理念には、外部からのデータを「利用する」という側面だけではなく、自分のデータを外部へ「公開する」側面も重要です。今後、データ共有を推進する企業は、ほとんどのビジネス価値指標において、 データ共有をしない他社を凌駕するとガートナーが予測する (英語)。従って、「原則共有しない」という従来の考え方から、「原則共有する」マインドセットへの転換が必要だと指摘されています。
「原則共有」モデルは、無計画なデータ共有を意味することではありません。会社の戦略や方針を加味した上で、ビジネス目標とデータ共有の整合性を図りながら、全スタッフの足並みを揃えるような環境作りをすることがポイントです。

上記図表の各ステップを簡単に解説しましょう。
- ビジネス目標の設定は、データ共有戦略により何を成し遂げたいかを明確化するために重要です
- その後、リスクの再検討・再調整を行い、情報共有によって被害を受ける可能性のあるケースを特定します
- 信頼性の管理は、データソース (データ源) の信頼性、及びデータ自体の信憑性を担保するための取り組みを指します
- 環境整備には、技術的な環境を整えることだけでなく、データ共有に対する組織全体の共通理解を図ることも含まれます
- データエコシステムの拡張とは、組織の内部データと、行政のオープンデータを含む外部データを融合させることを指します。プロセスの最適化・改善のために人工知能 (AI) や機会学習 (ML) を活用することもできます
このアプローチから得られる効果として、内部 (従業員) の関係深化と共に、顧客との関係改善があります。特に、顧客から得たデータをまた顧客に還元することで、カスタマーエンゲージメントや、ある種のコミュニティ性の創造につながります。例えば、ゲーム業界ではプレーヤー同士で平均成績を比較したり、エネルギー業界では光熱費などの平均値を知ることができれば、消費者にとっては貴重な判断材料となります。さらに、企業側もそこから顧客セグメンテーションなどに関わる有意義なフィードバックを得ることができ、好循環が生まれます。
活用事例 3
ZOZOのコーディネートデータ
2021年にファッションECサイトZOZOTOWNの運営会社が、ファッションアプリの ユーザーによるコーディネート約255万件を含む大規模データセットを公開しました。目的は、ファッションに関する課題解決を探るための研究開発を促進することです。
オープンデータの利用に関する注意点
オープンデータの利用において注意すべき点として、庄司氏は出典の明記が求められている場合があることと、一部のデータの形式が標準化されていないことを挙げています。同氏はその状況を料理に例えて注意を喚起しています。
特に行政のオープンデータは、自治体が異なると用語や形式が異なるなど、現時点では残念ながらデータ利用者として使い易いとは限りません。料理に例えると、カットされてすぐに料理に使える状態の野菜ではなく、泥がついたままの不揃いの野菜であることも多い状態である、ということを理解しておく必要はあると思います。
庄司昌彦 武蔵大学教授
コネクトデータが行ったオープンデータ活用に関する調査も、 データ収集・前処理などの準備や、データ活用を進めるためのコストなどの面で課題が残っていることを明らかにしています。
このような問題に対処する方法は、大きく分けて2つあります。 一つは社内のリソースを使うことですが、そのためには多種多様なデータ形式に対応できる データ抽出ツールや データ分析ツールの導入が必要です。もう一つの選択肢は、編集加工して販売されているデータを外部から購入することです。そういった編集加工ビジネスは、今後より成長していく可能性があると庄司氏は示唆しています。
いずれにしろ、オープンデータを利用の際には、自社の事業戦略に沿ったデジタル戦略を確立した上で、ソフトウェアなどへの投資を検討する必要があります。
DX戦略の一環としてのオープンデータ
小規模事業者・中小企業にとってのオープンデータの主なメリットは、データの入手や作成、分析、アプリ開発への活用などに関わるコストを低減できることと、開発者・活用者コミュニティとの接続によりツールや知見を得られることにあります。また、民間の企業も自身のビッグデータを公表することにより、DX (デジタルトランスフォーメーション) の深化に向けて相乗効果が期待できます。
もっとも、自社がオープンデータから何らかの利益を得るためには、活用機会を適切に検討し、その意義や目的を社内で共有する必要があります。それをクリアした上で、オープンデータ活用に適したツールの導入やルール整備に着手するべきでしょう。